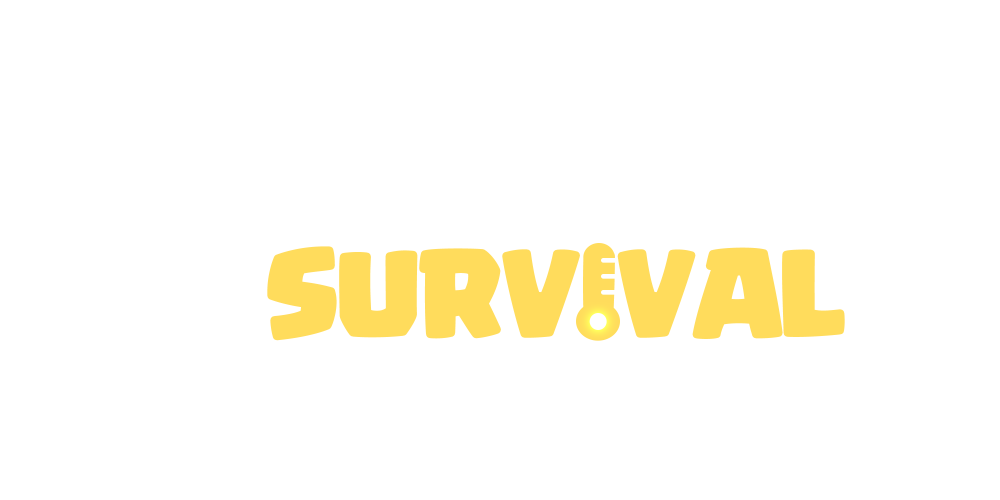「たとえ世界が滅んでも、自分の舌は裏切れない」…パトリック。
かつては太陽城の宮廷シェフとして、パトリックは人類最大の楽しみは美味しい食事だと信じていた。そして彼は人生の殆どを費やして美食を研究し、究極の味覚体験を追い求めた。やがて類稀な調理技術により、彼は国王や貴族から絶賛される存在となった。
しかし、ソラリス王朝の終焉と共にパトリックは職を失い、廃墟も同然の街に住むことになった。使える食材や調味料は僅かだったが、彼は落ち込むどころか複雑な料理をシンプルにする調理法を考案した。一般的な食材を不思議な魅力で輝かせようと、研鑽を怠ることは無かったのだ。
時には、パトリックも戦いを余儀なくされることがある(略奪者との遭遇、あるいはやむを得ない食材調達など)。彼は生まれてから戦闘訓練など受けたことはなかったが、何故か実戦での成果は悪くなかった。生まれ持った剛腕と、調理から学んだ格闘術(自称)のおかげだそうだ。
パトリックの調理技術は非常に優れていたが、斬新な創意工夫が毎回成功するとは限らなかった。意気込んで新しい料理を開発しても、初めて扱う食材を加えたことで、何とも珍妙な味に仕上がることもあった。つまり、彼の新作料理には一定のリスクが伴うのだ。かつてない喜びを感じることもあれば、同等の恐怖を感じる可能性もある。特にバシティは、それを思い知っているだろう。
宮廷シェフの地位を失った時、パトリックはすぐに楽観的になれたわけではなかった。人生の意義を永遠に失ったとさえ思っていた。だが、激しい吹雪が転機となった。その吹雪は長く、薄暗いシェルターにいつまでも閉じ込められ、人々は鬱々としていた。それはパトリックも例外ではなかった。
「どうせ死ぬのなら…」という気持ちで、彼は残った食材でみんなのために心を込めて「最後の晩餐」を調理した。しかし、久しぶりの美味しい料理を食べた人々は驚くほど元気を取り戻し、シェルターの消沈した雰囲気はガラリと変わった。そうして吹雪を乗り越えた経験が、パトリックに美食の真理を再発見させたのだ。

| パトリック | |
|---|---|
| 希少性 | |
| 階級 | |
| サブ階級 | |
統計
| 探検 | |
|---|---|
|
|
1776 |
|
|
2220 |
|
|
17760 |
| 遠征 | |
|---|---|
| 攻撃 | 140.1% |
| 防衛 | 140.1% |
パトリック
物語
欠片
|
星 | 階級 |
兵士レベル 1 | 兵士レベル 2 | 兵士レベル 3 | 兵士レベル 4 | 兵士レベル 5 | 兵士レベル 6 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
|
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
|
|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
|
|
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
|
|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
スキル
バーベキュー
大量の豪華な食事で、味方全体のHPをパトリックの攻撃力*200%/220%/240%/260%/280%分回復する。さらに味方全体の攻撃力が5%/5.5%/6%/6.5%/7%上昇する。4秒持続。
肉厚脂肪
料理人の肉厚脂肪により、自身の被ダメージが10%/15%/20%/25%/30%低下する。
非常食
いつもおやつを持っている。5秒毎に攻撃*50%/55%/60%/65%/70%分のHPを回復する。
幸せグルメ
パトリックは美味しい料理で味方を励ます。味方全部隊のHPが5%/10%/15%/20%/25%上昇する。
カロリー吸収
美食が戦意と潜在能力を刺激し、味方全部隊の攻撃力を5%/10%/15%/20%/25%上昇させる。